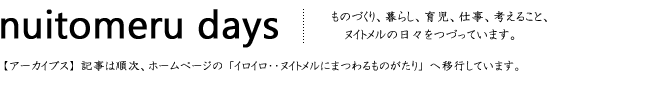革の素に思いをよせる
2014-2-20
革のはじまり
革のもとは動物の皮膚です。
太古の昔から、人々は動物の皮を利用してきました。
森の落ち葉に埋もれた水たまりに漬かっている動物の死骸が、肉は腐っても皮膚は腐っていなかったのを見つけたのが、人類が植物タンニン鞣(なめ)しを発見した時と言われています。これは、落ち葉や木切れからタンニン(渋・ポリフェノール)が水に溶けだし、天然のタンニン鞣しが行われていたと考えられます。
皮は紀元前から世界各地で、渋のほか灰汁や油など様々な方法で鞣されてきましたが、
19世紀のイギリスで、オークの木から抽出したタンニンを使った皮の鞣しが始まりました。
英語で tan は「皮を鞣す」、語源はオークを意味し、
製革をタンニング:tanning、鞣す工程担う人(製革業者)をタンナー:tanner と呼びます。
その後ミモザやチェストナット、ケブラチョなどの植物の樹皮や幹から抽出したタンニン鞣しは、
いつしか日本へもその技術が伝えられ、革の滑らかな表面をあらわす「ぬめり」を語源として、
タンニン鞣し革が「ヌメ革」と呼ばれるようになりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
皮から革へ
このように、「皮」は「動物の皮膚」から「鞣(なめ)し」という工程を経て「革」になります。
タンニン鞣しの革は非常に時間と手間がかかるため、当時はとても高価なものでしたが、
なめしの技法や染色染料、加工方法も産業革命の影響を受けて進歩していきました。
1850年代にクロムなどの金属を原料とした化学薬品による鞣し技術が開発され、
革の大量生産が可能となり、革という素材が一般的に使われるようになりました。
その後、合成皮革、人口皮革という人工的なイミテーション革も開発されて、
ますます革という素材が一般的、かつ安価に手に入るものとなりました。
現在、天然皮革の「鞣(なめ)し」の工程は、大きく分けて、クロム鞣し、タンニン(渋)鞣しの2種類です。
(ふたつを合わせる方法の混合なめしの他、油なめし・白なめしなど伝統的な鞣し技術もありますが、ここでは割愛します。)
鞣す工程も、タンニンの液体槽に皮を浸す「ピットなめし」、タイコと呼ばれる大きな容器を回して鞣す「ドラムなめし」という方法に分かれます。
また、製革の工程(鞣しと染色)は全てタンナーが担っていますが、
染色には2種類の方法、染料を浸み込ませる染料染めと、顔料を表面に吹き付ける顔料染めがあります。
前者は革の風合いがそのまま表れるのに対して、後者は表面のキズ等が隠せるため均一な仕上がりになり、
一般的に両者を掛けあわせて染色されることが多いようです。
クロム鞣しと顔料染めは色々な意味で比較的安価で大量に作ることに向いているため、
現在の天然皮革はほとんどがこの技法を取り入れて製革されています。
また、表面が均一に美しく柔らかい風合いになり、クロムなめしには固有の優れた面があります。
一方、タンニン鞣し革にしかない特質と独特の風合いも長く愛され続けており、現在も世界各地の革の産地で製革されています。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
つづきを読む → ヌイトメルの素材選び